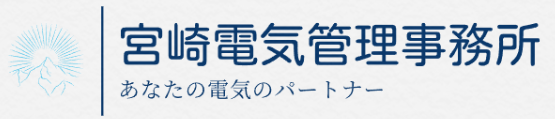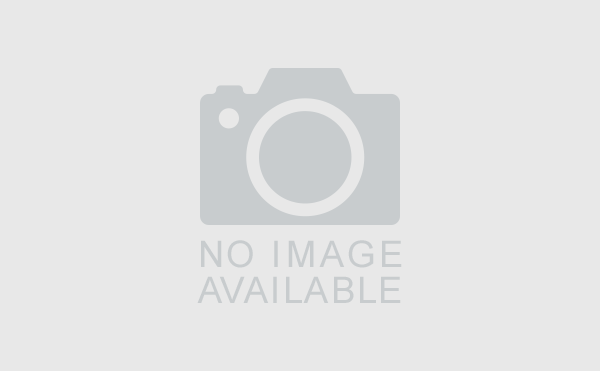高圧機器の絶縁抵抗値
電気設備の点検をしていると、技術者の間で話題になる事ががあります。
「高圧機器の絶縁抵抗値って、何MΩ以上あれば合格なんですか?」というものです。
意外に思うかもしれませんが、実はこれ、法律で明確に決まってないんです。
低圧と高圧では扱いが違う
低圧機器(600V以下)については、電気設備技術基準や内線規程で「0.1MΩ以上」みたいな具体的な数値がちゃんと書かれています。
ところが、高圧機器になるとその“合格ライン”がないんですよね。
何故決まってないの?
理由はシンプルで、高圧機器って種類も使い方もバラバラだからです。
変圧器、遮断器、ケーブル…それぞれ絶縁の構造も違えば、置かれる環境(屋外・屋内・湿気が多い場所など)も違います。
だから一律で「何MΩ以上」と線引きするのは現実的ではないんです。
じゃあ現場ではどうしてるの?
もちろん「何も基準がない」というわけではありません。実際には、
- メーカーが出している取説や試験成績書
- JISやJECの規格
- 過去の測定値との比較
- 耐圧試験の結果
こういったものを参考にして判断しています。また、所属している法人や協会によって、目安としている数値があります。
特に大事なのは「前回より下がってないか」とか「異常に低い値じゃないか」という“傾向”を見ること。
まとめ
つまり高圧機器の絶縁抵抗値は、法律で数字が決まっていないからこそ、現場では「数値そのもの」と併せて「変化や異常」をチェックするようにしています。
合否のラインではなくて、劣化やトラブルのサインを見つけるための指標、という感じですね。